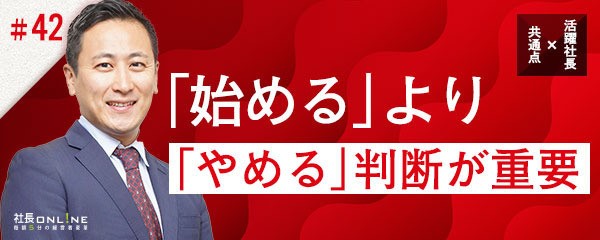アジャイル経営~環境に即応し、変わることに一切躊躇しない~
-
2025.05.26

- 事業の成長は、時に“増やす”こと以上に、“捨てる”ことが鍵を握る。創業からわずか15年で、売上10億円超を達成したある経営者の軌跡を紐解くと、規模拡大の本質が詰まっている。その成功の背後には3つの経営的視点があった――。
※本記事は士業事務所の経営者を取り扱う。士業はサービス専門職のため10億規模となるものの、一般事業会社において50億規模への成長思考を持つ人に読んでいただきたい
1.次の事業に集中するために、スパッとやめる
 経営者が最初に事業をスタートしたのは、特定の専門的サービスを提供する事務所からだった。売上はおよそ4,000万円。堅実ではあったが、成長の余地には限界が見えていた。
経営者が最初に事業をスタートしたのは、特定の専門的サービスを提供する事務所からだった。売上はおよそ4,000万円。堅実ではあったが、成長の余地には限界が見えていた。
そこで彼は、立地を都市部に移すと同時に、より市場規模と収益性を狙う事業に転換。その結果、売上は5億円を超えるまでに跳ね上がった。
だが、そこに安住しなかった。
十分に利益は出ていたが競争激化の兆しをいち早く感じ取った彼は、「まだ利益が出ているうち」に事業をやめ、次なるフィールドに再度舵を切る。タイミングは、同業他社が投資を進める段階だった。
多くの経営者は、少しでも利益が出ているうちは事業継続を選びがちだ。たとえ売上が右肩下がりでも、「過去に成功した実績」や「完全に赤字になっていない」という理由で、撤退を先延ばしにしてしまう。
この経営者が成功する社長だったのは、他社と違う判断軸を持っていた。
“まだ利益が出ているうちにやめる”という決断が、新たな集中と次の収益の土台を生み出した。まさに「何かを始めるためには、何かをやめなければならない」という真理を体現している。
2.体裁は意識せずに、利益ファーストに考えられる

画像提供:PIXTA
利益の最大化という観点から、経営者は事務所の立地も冷静に見直した。
元々、事業をBtoC向けに展開していた時は、ターミナル駅前の超一等立地にオフィスを構えていた。しかし、BtoB中心の事業に転換した際には、その高額なオフィスを潔く手放し、コストパフォーマンスに優れたビジネスエリアへとあっさりと移転を決める。
通常、一度華やかな駅前の一等地や、名のあるビルに入ってしまうと、たとえ業態が変わっても「格を落としたくない」「顧客や社員の目が気になる」といった理由から移転をためらう経営者は多い。
そこに“プライド”という名のコストが加わってしまう。
しかし、彼は、「見た目」よりも「実利」を重視する。
高コストな場所での営業は不要と判断すれば、即座に撤退。新しい立地は、事業内容に合致しており、顧客接点や信頼性を損なうことなく、利益率を高めることに成功した。
拠点の変更は、社内外に向けた強烈なメッセージでもある。「我々は今、何に集中するのか」場所の選定に体裁を挟まなかったからこそ、社員の意識も明確に切り替わった。
3.情報収集は欠かさずに時流を読むチカラがある

画像提供:PIXTA
変化に強い経営者は、例外なく「情報収集の質と量」にこだわっている。
この経営者もその一人だ。あるとき、自社の中核事業の将来性に懸念を抱き、ヨーロッパのデジタル先進国を視察。現地では、行政手続きの大半がすでにオンライン化されており、「代行業務」という自社の柱がいずれ不要になるという現実を、肌で感じ取った。
帰国後すぐに、人間にしかできないコンサルティング事業へとまたも軸足を移す。その行動の背景には、現場の情報だけでなく、グローバルな時流を掴もうとする貪欲さがある。
多くの経営者は、「海外視察に行っても現実を見たくない」「目の前の業務に集中していたほうが楽だ」と無意識に変化から目をそらしてしまう。しかし経営者は、変化を受け止めるために、自ら進んで現場を離れ、新しい情報に触れる時間を投資することが大事なのだ。
情報収集とは、単にインプットすることではない。
自分にとって都合の悪いことこそ受け止めて、必要と判断すれば行動する。
――それが、この経営者の強みだ。
業界平均を大きく超え、10億円を超える事務所へと成長した理由をまとめると、一言に集約される。
環境に即応し、変わることに一切の躊躇がない経営スタイル
いずれも、頭では理解できても、実際に行動に移すには勇気がいる。
変化が激しい時代において、その変化にしっかり対応していく。
それを「アジャイル経営」と言う。変化に迅速かつ柔軟に対応できるように、組織やプロセスを機敏に動かす経営手法のことだ。
今のような時代にスケールするためには、アジャイル経営が必須と言える。