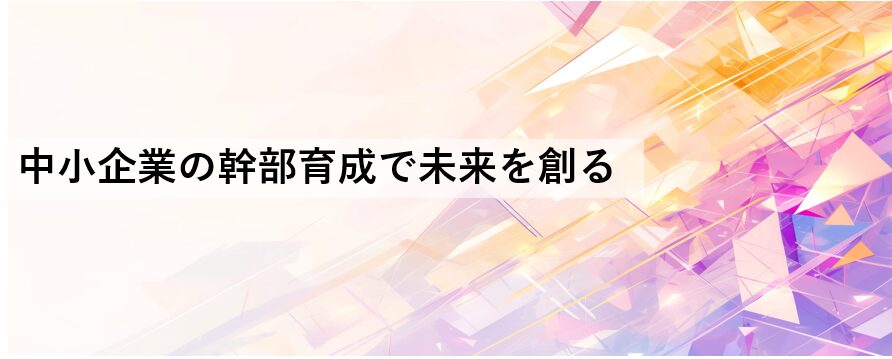中小企業の幹部育成で未来を創る
-
2025.05.27

- 中小企業の幹部育成は喫緊の課題です。成功の鍵は時間、選択肢、実践的な育成方法にあります。
総括
多くの中小企業が直面する幹部育成の課題に焦点を当て、その解決策を探ります。
後継者や任せられる幹部がいないという経営者の悩みは多く聞かれますが、これは後継者候補や幹部候補となる人材の選択肢を自ら狭めてしまっているケースが多いことが原因です。幹部育成には、単に業務スキルを継承するだけでなく、経営者としての能力や価値観を時間をかけて醸成することが不可欠です。
幹部候補を育てる実践的な方法として、新規事業への挑戦が非常に有効です。新規事業を通じて、経営全体の理解や意思決定能力を養うことができます。不採算部門の立て直しや他部門の責任者経験、経営会議への参加なども、経営者視点を獲得する貴重な機会となります。
特に、伸びる会社のナンバー2は、社長の強みを補う逆のタイプが多い傾向にあります。社長との継続的な対話や社外の専門家を交えたコミュニケーションも幹部育成においては重要な要素となります。幹部候補を見つける基準としては、まず結果を出す力があり、広い視野を持てる人材が望ましいです。そして、会社が幹部に何を求めているのかを明確にし、その基準やプロセスを可視化し共有する努力が、幹部育成の成功確率を高めます。
中小企業が直面する幹部育成の現状と課題
多くの中小企業経営者様から、「後継者がいない」、「次に会社を任せられる幹部が育っていない」というお悩みの声をお聞きします。
これは非常に深刻な課題です。しかし、その多くは、実は幹部候補となる人材の選択肢を、知らず知らずのうちに自ら狭めてしまっているケースであると私たちは感じています。例えば、「後継者は親族から」といった固定観念や、「うちには任せられる人材はいない」といった思い込みが、育成の機会を逃している可能性があります。
幹部育成は、単に既存の業務やスキルを引き継ぐことではありません。経営を任せられる人材を育てるというのは、単なる業務の継承ではなく、社員や取引先からの信用、経営者としての総合的な力、そして意思決定の経験など、多岐にわたる要素を育成することです。これらは一朝一夕に身につくものではなく、時間をかけてじっくりと醸成していく必要があります。また、企業の根幹をなす価値観を幹部候補に浸透させるためにも、やはり十分な時間が必要になります。こうした時間と選択肢の重要性を理解することが、幹部育成の第一歩となります。

幹部育成成功の鍵となる「時間」と「選択肢」
幹部育成において、まず重要な要素は「時間」です。
経営を担う人材を育てるためには、単なる業務の引き継ぎやスキル研修だけでは不十分です。企業全体の価値観や理念を深く理解し、経営者としての視点や判断基準を身につけるには、経験の積み重ねと内省、そして周囲からの信頼を得るプロセスが必要であり、これには長い時間が必要となります。例えば、重要な意思決定の場に立ち会わせたり、そのプロセスに関与させたりといった経験は、時間をかけてこそ血肉となります。
次に重要な要素は「選択肢」です。後継者候補や幹部候補を探す際に、特定の枠にとらわれず、幅広い可能性を検討することが成功の鍵となります。親族内承継はもちろん主要な選択肢の一つですが、それだけに固執する必要はありません。社内からの抜擢・昇格、外部からの優秀な人材の招聘、あるいはM&Aによって迎え入れる経営人材など、様々な手段を視野に入れるべきです。選択肢を多く持つことで、自社に最も適した人材を見つけ出し、効果的な幹部育成計画を実行することが可能になります。船井総研の調査でも、後継者が決まっていない企業が多い中で、親族以外からの承継を考える経営者が増えている現状が見られます。
新規事業への挑戦は優れた幹部育成手法
幹部育成の具体的な手法として、新規事業への挑戦は非常に効果的です。
新規事業を立ち上げるプロセスは、経営者としての資質を磨く絶好の機会となります。事業計画の策定から資金繰り、PLやBSといった会計知識の習得、そして市場との向き合い方まで、経営の根幹を体感しながら学ぶことができます。
新規事業での成功体験は、幹部候補自身の自信につながるだけでなく、社内からの信頼や求心力を高めることにも寄与します新規事業の初動は大変ですが、その苦労を乗り越える経験こそが幹部候補を鍛えます。社長は成功確率の高い事業を選定し、資金面や人的な支援を含め、立ち上がるまで忍耐強くバックアップすることが重要です。この経験を通じて、苦楽を共にした人材が将来の右腕やパートナーに育っていくのです。

社長の右腕・ナンバー2の見つけ方と育成のポイント
成長している会社には、社長にとって優れた右腕、すなわちナンバー2が存在することが多いです。
この右腕を見つけ、そして将来の経営を任せられる「頭」や「体幹」へと育てていくことが、幹部育成の重要なプロセスとなります。長年経営されている会社には、既に右腕や左腕と呼べる存在がいることが多いですが、彼らをどう次のリーダーとして育成するかが課題です。そのためには、社長と同じ視点で物事を捉え、責任や重圧を知る経験を積ませることが必要です。
具体的な育成方法としては、新規事業の立ち上げや、逆に不採算部門の立て直しといった困難なミッションを任せることが挙げられます。また、営業部門の責任者に管理部門を経験させたり、管理部門の責任者に営業部門を経験させたりすることで、企業全体の構造理解を深めさせます。顧客対応の最前線であるクレーム対応の責任者も、顧客の声と現場の苦労を知る貴重な経験となります。
さらに、取締役会や経営会議の事務局を務めさせ、意思決定プロセスを肌で感じさせることも有効です。これらの部門責任者経験は、最低でも3年程度行うことで、その部門をより良くするためのKPI設定などにもコミットできるようになります。伸びる会社のナンバー2は、社長の長所・短所を自己分析した上で、社長と逆のタイプであることが多く、社長の意図を具現化する力を持っています。
幹部候補を選定し、成長を促すための基準と環境
幹部育成を進める上で、どのような人材を幹部候補とするかの基準を明確にすることが重要です。
まず大前提として、担当する事業や業務において結果を出している人材が幹部候補の対象となります。単に個人の力だけでなく、周囲の力を引き出し、チームで結果を出せる人材は、人をまとめる素質があると言えます。さらに、自社のことだけでなく、業界全体、日本国内、さらには海外といった広い視点で物事を捉え、自社の立ち位置やあるべき姿を考えられる人材も重要です。
社内から幹部候補を育成することには、カルチャーフィットしやすく、社内の納得感を得やすいというメリットがあります。一方で、派閥争いや前経営者の影響が残りやすいといったデメリットも存在します。こうしたリスクを抑えながら、幹部育成を成功させるためには、会社が幹部に何を求めているのか、どのような資質や能力が必要なのかを明確に定義し、その選定プロセスや基準を極力可視化して社内と共有する努力が必要です。
幹部に求める要素は、形式知化が難しい暗黙知の部分も多くありますが、社長と幹部候補、そして既存幹部間での対話を通じて、この暗黙知を形式知化し、共有していくプロセスが、幹部育成を成功させる鍵となります。幹部候補自身が明確な目標を持つことも、成長のためには不可欠です。