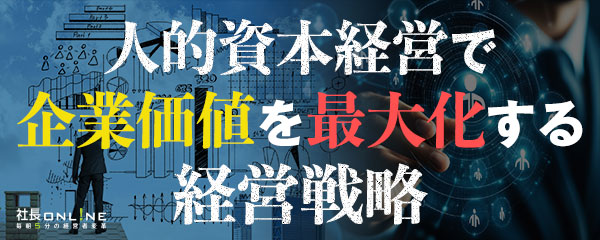人的資本経営で未来を創る中小企業経営者ガイド
-
2025.07.10
人的資本経営とは?経営者が知るべき本質
人的資本経営は、現代の企業経営において最も重要なテーマの一つになります。
人的資本経営とは、一般的に人材を単なる「資源」ではなく「資本」として捉える経営のあり方を指します。これは、人材を投資対象と見なし、その価値を最大限に高めることで、最終的に企業全体の価値向上を目指す経営手法です。
特に世界的に無形資産への注目が高まる中で、この人的資本経営の重要性はますます増しています。例えば、米国経済の成長は無形資産の豊富さに支えられており、ソフトウェアやブランド価値のような「見えざる資産」が企業価値を大きく左右する時代です。
日本においては、先進国の中でも生産性の低さや賃金の伸び悩みが課題とされています。政府もリスキリング(学び直し)を提唱し、人の能力を高めることで国全体の生産性向上を目指す動きが加速しています。この状況下で、上場企業には人的資本情報の開示が義務付けられるなど、企業が人的資本をどのように可視化し、投資していくかが問われています。
しかし、多くの中堅・中小企業では、「具体的に何をすれば良いのか分からない」という悩みを抱えているのが現状です。私たち船井総合研究所は、この人的資本経営こそが、企業が生産性を高め、賃金を引き上げ、ひいては業績を向上させるための鍵であると確信しています。
経営者のための人的資本経営戦略:船井総合研究所のアプローチ
私たち船井総合研究所が提唱する人的資本経営の核心は、「業績アップ」に直結させることです。
多くの企業で事業戦略は綿密に立てられていますが、それに伴う人員計画は「人は無限にいる」という前提で立てられがちです。しかし、人手不足が事業の推進を阻害する状況は、今や多くの産業で顕著になりつつあります。この課題を解決するためには、単に人員を採用するだけでなく、戦略的な人材配置転換や、リスキリングによる育成が不可欠になります。
船井総合研究所では、以前からこの人的資本経営の考え方を実践しています。例えば、コンサルタントを人事部門へ異動させたり、ベテランコンサルタントを戦略的に異なる部門へ配置転換したりすることで、組織全体の生産性向上を図ってきました。特に2018年からは、DXコンサルティングと中堅企業開拓を二大テーマに掲げ、これに合わせて人材ポートフォリオの組み直しや評価制度の変更を行い、新卒と中途採用のバランスまで見極めています。
これらの人的資本経営への取り組みが、私たち自身の業績好調に繋がっていると実感しています。結果として、一人当たりの粗利は年々上昇し、特に若手社員の生産性は飛躍的に伸びています。これは、人事組織の確立、教育体制の改善、そしてITツールの導入による人的資本経営の成果と言えます。

※画像提供:PIXTA
人的資本経営で最大化する「従業員ライフタイムバリュー」
人的資本経営を成功させる上で、私たちが重視している指標の一つに「従業員ライフタイムバリュー(ELTV)」があります。これは、マーケティングにおける「顧客の生涯価値」と同様に、従業員が企業にもたらす生涯価値を指します。
採用が困難になり、離職率が増加している現代において、このELTVをいかに高めるかが喫緊の課題になります。ELTVを高めるには、主に「生産性(1人あたり粗利額)」と「在籍年数」という二つの要素を考慮する必要があります。
企業は、優秀な人材を獲得するために多大な採用コストをかけています。しかし、採用後の取り組みがなければ、その投資は十分なリターンを生み出しません。採用した人材に高いエンゲージメントで働いてもらい、会社に高付加価値で貢献してもらうことで業績を伸ばし、その利益をさらに人材投資(平均年収の引き上げ、福利厚生の充実、オフィス環境の整備など)にまわりすという好循環を築くことが、人的資本経営の理想的なかたちです。
在籍年数の目標は産業や業種によって異なりますが、例えば新卒採用が多い企業では、在籍年数が短くなる傾向にあります。自社の現在の在籍年数を把握し、それを1年でも長くすることで、人材投資のリターンを最大化する視点を持つことが、人的資本経営において極めて重要になります。
人的資本経営の具体的な指標:KPI設定と活用
人的資本経営を推進するためには、定量的指標(KPI)を設定し、活用することが不可欠です。
単に全社員の離職率を見るだけでなく、例えば「営業部門の離職率」「入社3年以内の離職率」「入社1年経過社員の離職率」など、多角的な視点からデータを分析することが重要になります。これは、顧客セグメントごとにマーケティング戦略を立てるのと同様に、社内の人材を細分化して課題点を見つけ出すアプローチです。これにより、「新卒の3年以内離職率が高いので、この層への育成・定着施策を強化すべき」といった具体的な改善ポイントが浮き彫りになります。
私たち船井総合研究所では、まず10年間のロードマップを描くことをご提案しています。その上で、10年後の企業イメージを持ちながら、まずは3年間の具体的な中期目標を設定し、その進捗を定期的に定点観測していくことが大切です。
また、採用活動「以外」の視点も重要になります。事業ポートフォリオと人材ポートフォリオを連動させ、必要に応じて人員の配置転換や、アウトソーシング・業務委託の活用、あるいは一部の採用停止も視野に入れるべきです。特にスタートアップ企業で多く見られる業務委託の活用は有効な手段ですが、私たち船井総研では「長期インターン」を推奨しています。これは、コストを抑えつつ学生に業務を切り出し任せることで、実質的なアウトソーシング効果と将来の採用投資を両立できるからです。

※画像提供:PIXTA
経営者の責務:人的資本経営における人材ポートフォリオの最適化
人的資本経営における人材のバランスとポートフォリオの最適化は、経営者が主体的に判断すべき最重要事項になります。企業には、既存事業の生産性維持・向上と、新規事業への挑戦という二つの側面があります。既存領域では、若手社員の生産性向上に注力し、安定的な成長を追求します。一方で、M&Aや新規事業開発のような挑戦的な取り組みには、相応の投資とリスクを覚悟して臨む必要があります。重要なのは、企業が余裕のある成長期に、次のチャレンジに取り組める体制を構築することです。
多くの企業では、社員のキャリアパスが「マネジメントライン」一辺倒になりがちですが、人的資本経営では、マネジメント層、スペシャリスト層、そしてオペレーションを支える層といった、バランスの取れた人材ポートフォリオを構築することが求められます。
そして、それぞれの役割に合わせた評価制度を設けることで、人材の最大限の活躍を促すことができます。かつて私たち自身も、ホワイトボードに社員の顔写真を貼り、事業と人員を紐付けながら配置を検討するようなアナログな手法を取っていました。今ではこれをデジタル化し、リアルタイムで人材の過不足を把握できる状態にあります。これにより、マネジメント層の不足に応じて採用や配置を迅速に調整することが可能です。このようなシステム構築は難しく感じられるかもしれませんが、多くの企業で実現可能であり、特に初期構築においては外部の専門家に任せることで、時間とコストを大幅に削減できるという知見もございます。
人的資本経営は、10年先を見据え、3年ごとの中期目標を設定し、事業と人材のポートフォリオを連動させながら、継続的に議論し改善していくことで、必ずや企業価値の向上に繋がります。

※画像提供:PIXTA